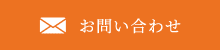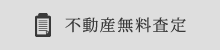「抵当権」とは、どんな意味を持つのか

多くの人が住宅を購入する際に住宅ローンを組みます。今は、35年という長期で設定し、月々の支払いを低くする人が多数でしょう。
しかし、家族のあり方は様々で子どもの進学や留学、両親の介護、転勤をはじめ夫婦間の様々な諸事情等、予想しないことが起きるのが人生です。
住宅ローンが残っているのに不動産を売却しなければいけないことになった際、どうすれば良いでしょう。その時、重要なのは「抵当権」です。
住宅ローンを組む際、金融機関は対象となる不動産に抵当権を設定します。抵当権は、もしローンが返済できなかったときの担保となるものです。担保とは、「万が一支払いが困難となった場合に、債務者に提供させるもの」を指します。
返済が滞った際、この不動産を競売にかけることで融資した金額を回収することができるのです。ローンの返済が滞れば、誰が所有していようとその住まいは競売にかけられてしまうため、抵当権付きの住まいを購入しようとする人は、通常はあまりいないでしょう。
一般的には売却するために、設定された抵当権を抹消する必要があります。
抵当権を抹消する方法
では、抵当権を抹消するにはどうすれば良いのでしょう? 抵当権抹消の第一条件は、ローンの完済です。しかし、ローンの支払いが苦しいから売却したいという方もおられます。
実際の取引では、売却代金を受け取ったと同時に、その資金をローン残高に充てることで抵当権を抹消する…という対策をとります。
売却した代金でローンを完済し、抵当権を抹消できることになります。
売却金額がローン残高よりも低かった場合は、買い換えローンを利用するという方法もあります。
これは、新たにローンを組み直すことで、メリットとデメリットがあります。
メリットは、以前組んでいた住宅ローンより安い金利で組み直せる可能性があるということでしょう。
デメリットは、土地価格が下落した際、売却損になる恐れがあることです。
いずれにしても抵当権が抹消すると共に、購入した不動産の抵当権が新規で発生するので、タイミングに気をつけて慎重に行ってください。
抵当権付きの不動産を相続した場合

親や親戚から不動産を相続するという体験は、あまり頻繁に起こることではありません。人生で1度だけ…あるいは経験しない方もおられるでしょう。だからこそ、よくわからないままに相続し、後で困るケースが増えています。
相続した不動産に抵当権が残っていることが後からわかった場合、どうすれば良いでしょう。
まず抵当権を抹消しなければ売却ができません。
しかし、亡くなられた方がその手続きをしていなければ、相続人が印鑑証明書を添付し必要書類を法務局に申請する必要があります。
もし、相続人が自分だけではない場合は、相続人全員の署名、捺印、印鑑証明書が必要になります。
手続きを複雑に感じたら専門家に相談するのもベターかもしれません。
・お問い合わせフォーム
https://www.toplife.jp/contents/category/contact/
・不動産を売りたい方
https://www.toplife.jp/contents/category/sell/
・オフィシャルサイト
https://www.toplife.jp/