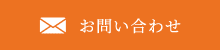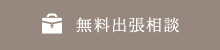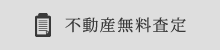「成年後見人制度」の種類について

「高齢の親が判断能力を失ってしまい、不動産の相続に困っている」といったご相談を受けることが増えてきました。
そのような際は、どうすれば良いのでしょう。高齢者の財産管理のための「成年後見人制度」というのをご存知ですか?
その制度について解説いたします。認知症などにより判断能力を失う前と後では、利用する後見人制度が異なりますのでご注意ください。
不動産所有者が将来、判断能力を失った際に備えて活用するのが「任意後見制度」です。こちらは、判断能力を失う前に契約によって後見人を決めておく制度です。
既に認知症などを発症し、判断能力を失っている場合は、「法定後見制度」が該当します。この制度は、「後見、保佐、補助」の3つに分けることができます。それはご本人の判断能力の程度によって区別されます。
「任意後見制度」について

事前に後見人を決めておく、「任意後見制度」について確認していきましょう。
この制度のメリットは、財産の所有者が自分の意見や意志を反映させることができるという点です。
ご自身の財産相続について将来的に心配な方は、元気で判断能力があるうちに任意後見制度を活用することをおすすめします。
具体的には、公正証書を作成し、後見する人(任意後見人)を契約で決めておきます。あらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督します。
そしてご自身の健康や判断能力が心配になってきた際、家庭裁判所に申し立てをし、任意後見人が任意契約で定められた財産管理などを行います。
「法定後見制度」について?後見人による実際の不動産手続き

「法定後見制度」について確認していきましょう。この制度は「後見、保佐、補助」の3つの区分があります。まず、「後見」とは、判断能力がほとんどない人を対象にしています。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任、成年後見人は本人の財産に関する全ての法律行為を本人に代わって行うことができます。
「保佐」というのは、判断能力が著しく不十分な人が対象です。
そして、「補助」というのは、判断能力が不十分な人が対象です。
では、成年後見人が着任した後の不動産管理について解説します。本人の居住用不動産売却には、家庭裁判所の許可が必要です。
手続きの流れとしては、成年後見人が本人の代わりに不動産業者と売買契約を締結します。次に、家庭裁判所に許可を申し立てます。その際は、売買の詳細、処分の具体的な内容が明らかであることが条件です。
また申し立ての実情(本人の生活費、入院費等)も明確に記載して問題がなければ、申し立て後、約1~2カ月で許可が下ります。
その後、法務局に不動産登記を申請します。この場合は、登記関係書類は、司法書士などの専門家により申請されることが多いです。
・お問い合わせフォーム
https://www.toplife.jp/contents/category/contact/
・家、貸しませんか?
https://www.toplife.jp/lp/
・不動産を売りたい方
https://www.toplife.jp/contents/category/sell/
・オフィシャルサイト
https://www.toplife.jp/